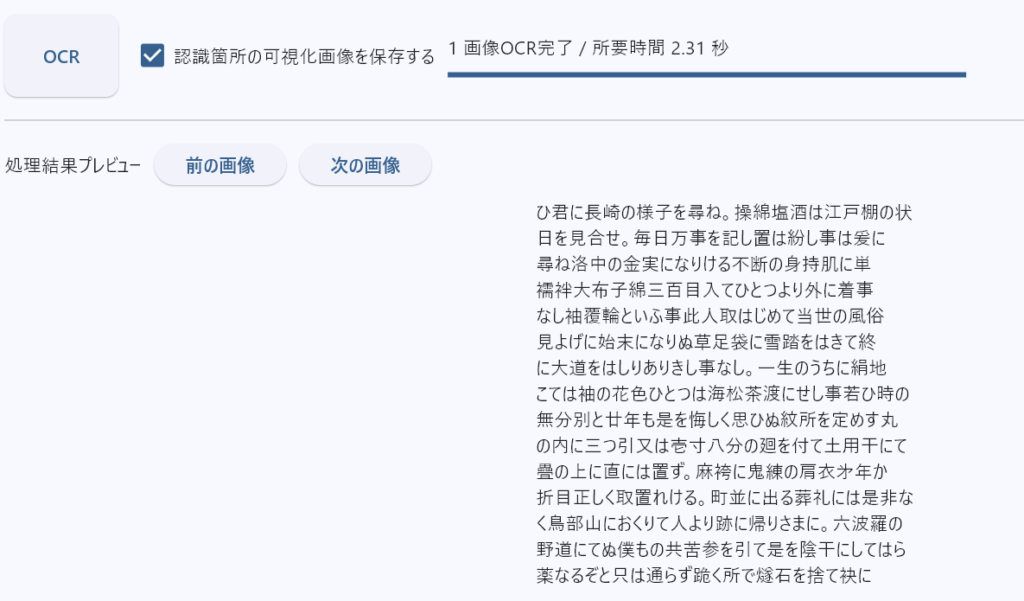本を読むと様々な情報が書かれています。ビジネス書や小説、図鑑といった様々な本を読めば役に立つ情報や面白い内容が書かれています。
ところが
本を読み終わった後に何が書かれていたかがまるで覚えていない人がいます。
本を読んでも記憶に残すことができない人は1冊の本を読んでも自身のためになっていないということです。これでは本を読む意味がありません。ただの時間の無駄をしているだけになります。
忘れてしまう読書はなぜ起こるのか?
本を読んでも忘れてしまう。ひどいときにはページをめくると前のページに書かれてあったことを忘れてしまう。そんな人もいます。
なぜ忘れてしまうのか。それは本の内容を目で追っているだけだからです。マンガを読むように読み飛ばしをしているか。集中できていないためです。
本の内容を覚えるためにはいくつかの方法があります。
・集中して本を読む。
・何度も繰り返し読む。
・感情をのせて読む。
・目次から内容を想像して読む。
・ほんのレビューやまとめを書く。
5つの方法をあげました。1つずつ説明していきます。
・集中して本を読む。
昔からいわれることですが、本は集中して読まなければ頭の中に入ってきません。テレビを見ながら本を読んでも単語のいくつかは覚えているかもしれませんが、内容を正確に理解はできません。
本に目を通せば内容を覚えているという天才は除外しますが、普通の人はそんな状況で覚えることはできないでしょう。
集中して読むときに大切なことは、自身の集中力がどの程度継続するかを知っておくことです。普通の人の集中力は15分程度といわれています。
集中力は休憩を入れることで回復をするのでこまめな休憩を入れて読み続けるのもよいでしょう。
もちろん、寝食を忘れて最後まで読んでしまう本というのはありません。読む出したら気づけば朝が明けているという本もあります。
・何度も繰り返し読む。
小説には向かないですが、技術書や学問書などでは覚えるまで読み返すという方法です。知り合いの話ですが同じ本を三回繰り返し読んでいます。1度目は気になった内容のページに付箋を貼り、2度目は付箋の張った内容にかかわる内容をノートにまとめていきます。3度目読むと内容が頭に入ってくるそうです。
良い本は100回読めといわれるように多読を行うと本の内容に対しての深度が変わってくるために著者が伝えたかった意味が変わるそうです。
・感情をのせて読む。
感情をのせるというのは言葉にすると分かりづらいかもしれません。例えば小説を読んでいてあまりに悲劇な内容に涙を流した内容は人間は簡単には忘れません。これは人間が生物の生存競争として恐怖を感じるとそのことを忘れられなくなり、同じ間違えが繰り返さなくなるということと同じです。
その方法をそのまま読書に生かすことができます。小説なら内容に涙し、笑い、喜ぶことで小説の内容を感情にのせて記憶することができます。
学術書でも初めて知った内容に驚きくことで記憶することができます。
・目次から内容を想像して読む。
小説にはあまりお勧めはできませんが、目次を見るとその項目に書かれている内容を指し示す内容が書かれています。その題目を見て内容を想像します。
例えば
『吊り橋効果は本当に効くの?』という題目だった場合、どんな内容化を想像してから本を確認します。書かれている内容はつり橋効果の説明や実験の内容など書かれ最後につり橋効果に効果についての話が書かれているので、想像した内容が当たっていればそのまま斜め読みや読み飛ばしをしてよいですし、外れていれば外れたことに対しての外れたことの気持ちが感情のフックとなり記憶が残るのでその内容を覚える可能性が高まります。
こういったテクニックはもともとある程度、同じ方向性の本を何冊か読んでいないと難しいです。
ちなみにつり橋効果はカッコいい人のみ効果があります。相手を見てこの人ならアリかなと思う人に対しては効果があるのですが、異性への恋心が発生しない相手には意味がないそうです。
・本のレビューや読書メモを書く。
この手法も昔から言われている有名な方法です。本の内容をコンパクトにまとめるということは内容を理解していないとできません。レビューや読書メモを書くことを前提に読む場合はしっかりと意識して読むようになります。
最後にもう一つ、『思考の整理学』外山滋比古さんなど様々な人が本に書いているのが、頭が最も働くのは朝起きてすぐの状態とのことなのでしっかりとした睡眠をとった後に目を覚ましてからすぐに本を読むという方法も一つの手ではないでしょうか。